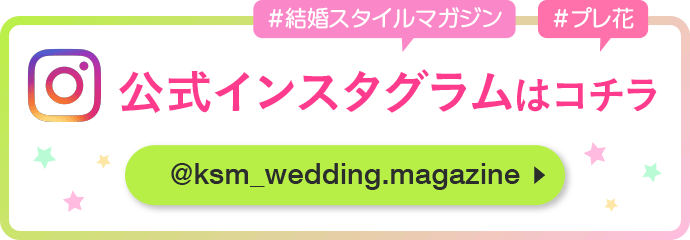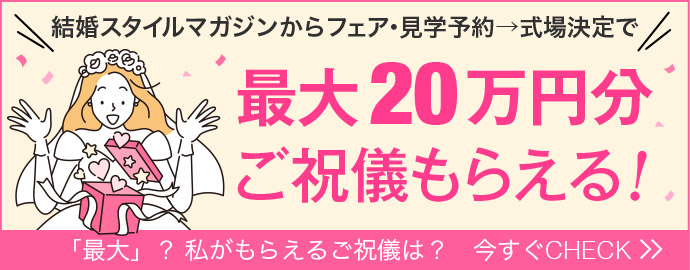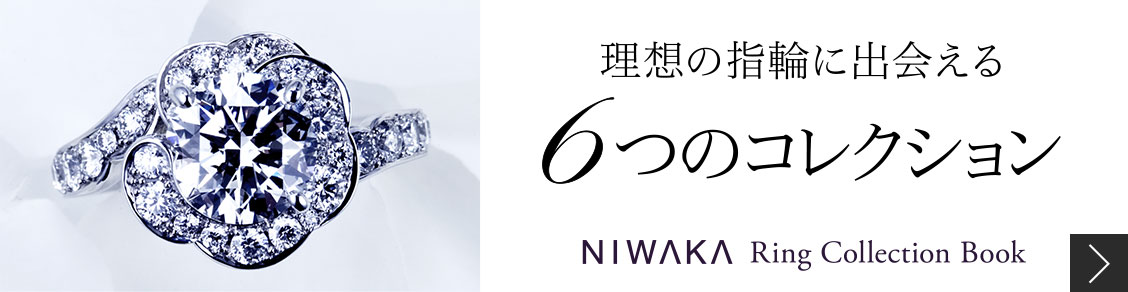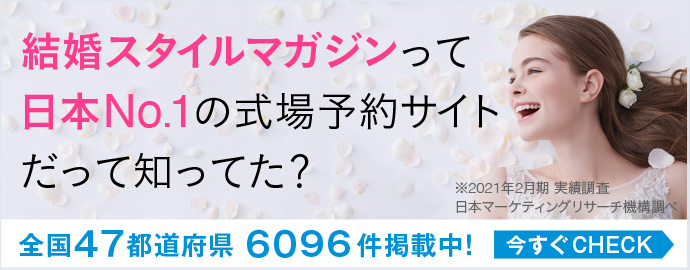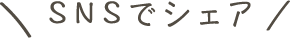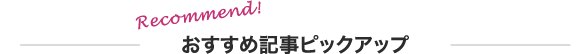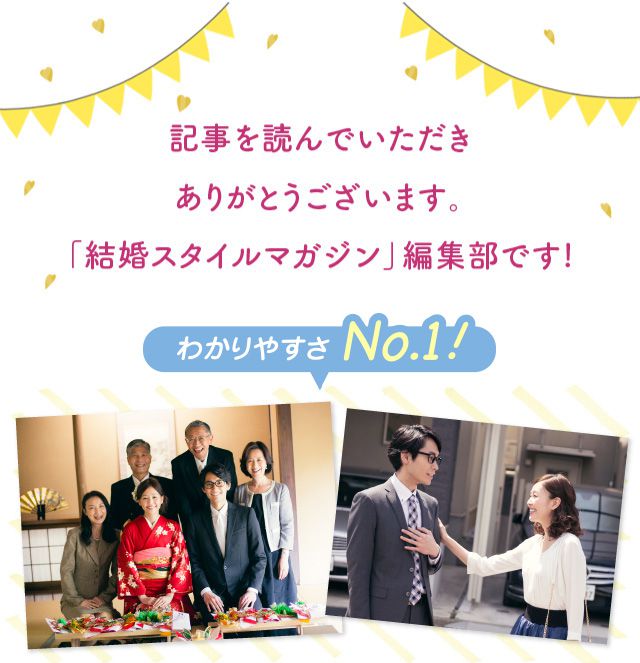【結婚式ご祝儀の相場】いくら包む?マナーは?会社・友人・親族など立場別に解説!
音声で聴く!
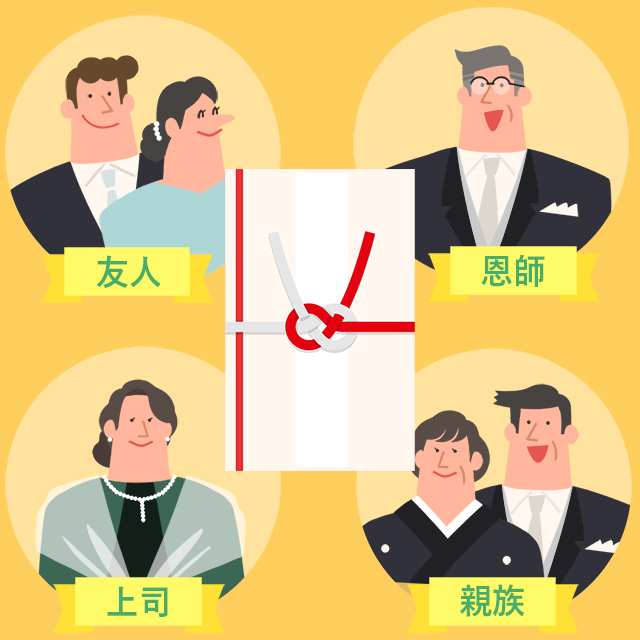
「ご祝儀っていくら包めばいいんだろう?」
結婚式に出席するとき、悩めるマナーの1つですよね。
そこで頼りになるのが、ご祝儀の相場。
上司、友人、親族など、ご祝儀を渡す相手別に相場をご紹介します。
さらに、夫婦で出席する場合や結婚式を欠席する場合など、シチュエーション別の相場も解説!
ぜひ参考にしてくださいね。
【ご祝儀の相場】3万円が基本
ひとりあたりのご祝儀には、基本となる金額があります。
その金額は、3万円。
なぜ3万円なのでしょうか?
ご祝儀には次の金額が含まれていると言われています。
・披露宴の食事・引き出物代の約2万円
・「お祝いの気持ち」1万円

これを合わせて「3万円」になるというわけですね。
ご祝儀は、この基本の3万円から新郎新婦との関係性を考えて、きりの良い金額になるよう金額を調整します。
新郎新婦とのお付き合いが深い場合や、新郎新婦よりも地位や年齢が高い場合は、多めに包むといった感じですね。

またご祝儀では、割り切れる「偶数」は別れを連想させるとされ、避けるのが一般的。
また「4」と「9」もそれぞれ「死」と「苦」を連想させるとされ、一般的に避けられています。
ただし偶数でも「末広がり」を意味する
8万円や、きりの良い10万円はOKだとされています。

最近では2万円も、「ペアだから」という理由でOKとされることもあるようです。
偶数になるのが気になるという場合は、1万円札1枚と5千円札2枚にするといいかもしれませんね。
ご祝儀の基本的な金額とマナーはわかりましたでしょうか?
では続いて、渡す相手別のご祝儀相場を見ていきましょう。
立場別のご祝儀相場
友人
友人へのご祝儀の相場はこちら。
| ゲストから見た 新郎新婦は? | 最多回答金額 (割合) |
|---|---|
| 友人 | 3万円(73.8%) |
「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」より
以下、データ出典元は同様
友人の場合、年齢に関係なく3万円が一般的です。
ただ、まだ学生や社会人1・2年目だったりすると、3万円包むのはどうしても難しい場合もあるかもしれません。

その場合は、2万円のご祝儀でも失礼にはならないとの声もあるよう。
2万円をご祝儀に包むケースについてはこちらの記事で詳しく取り上げています。参考にしてみてくださいね。
結婚式ご祝儀に「2万円」を包むのはどうなの?金額のマナー教えて!

会社関係(上司・同僚・部下)
続いては、新郎新婦が会社関係者の場合のご祝儀相場です。
| ゲストから見た 新郎新婦は? | 最多回答金額 (割合) |
|---|---|
| 部下 | 3万円(62.4%) |
| 同僚 | 3万円(71.0%) |
| 上司 | 3万円(66.8%) |
会社関係者へのご祝儀は3万円が相場のよう。
また仕事の取引先の人にご祝儀を贈る場合も、同じく3万円が相場のようです。

ただ、新郎新婦よりも立場がかなり上の場合は、主賓として招待されることもありますよね。
主賓には、一番上座の席を用意したり、ランクが違う引き出物を用意したりと、新郎新婦が特別な配慮をする場合も多いもの。
ですので、主賓として招待される場合は、少し多めの5~10万円のご祝儀を用意しておく人が多いようです。

主賓として出席するケースについては次の記事で詳しく取り上げています。参考にしてみてくださいね。
親族(兄弟姉妹・いとこなど)
最後に、兄弟姉妹やいとこなど、親族へのご祝儀の相場を見ていきましょう。
| ゲストから見た新郎新婦は? | 最多回答金額 (割合) |
|---|---|
| 兄弟姉妹 | 5万円(39.7%) |
| おい・めい | 5万円(33.2%) |
| いとこ | 3万円(49.6%) |
親族の場合、相場はちょっと高め。
家族で招待されるケースが多いのと、特別お祝いしたいという気持ちからかもしれませんね。
親と一緒に家族で招待されている場合は、親がご祝儀を1つにまとめて渡すので、個人で用意する必要はありません。
一方、家族とは別に個人で招待されたという場合は、個別にご祝儀を用意したほうがよさそうです。

なお、兄弟姉妹やおい・めい、いとこといった親族の場合、ご祝儀を渡す、渡さないは状況によってさまざま。
「結婚式でご祝儀を渡し合うことになるから、お互いご祝儀はなしにしよう。
引き出物も用意しないことにしようね。」
といったように、あらかじめ親族で話し合っているケースもあるようです。

でも、せっかくの結婚式に何も渡さないのもさみしいもの。
そういう場合はお祝いとして、何かプレゼントを準備するといいかもしれませんね。

兄弟姉妹へのご祝儀についてはこちらも参考にしてみてください。
兄弟・姉妹へのご祝儀や結婚祝いはどうする?相場や渡す際のマナーも解説!
続いては、イレギュラーな場合のご祝儀について、ケース別に紹介していきます。
ケース別のご祝儀相場
夫婦や家族で招待された場合
結婚式には、夫婦連名で招待される場合や、子供も含む家族で招待される場合もありますよね。
そんなときはどうすればよいでしょうか。

夫婦で招待された場合
夫婦で出席する場合、ご祝儀は1人分ずつ準備するのではなく、2人分まとめて準備します。
その場合の相場は5万円になります。
1人当たり3万円が相場だとして、本来なら夫婦2人分で6万円。
ですが、偶数を避けてきりの良い金額にするのが一般的なため、「5万円」とするわけですね。
夫婦で出席する場合のご祝儀はこちらの記事でも紹介しています。
子供も一緒に家族で招待された場合
夫婦二人分の5万円をベースとして、子供の分の金額を追加するのが一般的です。

追加金額を決めるときは、「子供に用意される料理」を基準にして考えましょう。
子供1人あたりの目安は次のとおり。
| 料理なし(赤ちゃん) | 追加なし |
| 子供用プレート | プラス5千円 |
| 大人と同じ料理 | プラス1万円 |

また、キッズスペースや授乳室の用意などをしてもらった場合は、感謝の気持ちを込めて5千円ほどプラスするとよいでしょう。
ただし、ご祝儀の合計額は5千円単位の端数が出ないよう、きりの良い金額に調整するのが一般的。
そのため、端数の分はプレゼントを買って渡すのがおすすめですよ。
また、社会人などのもっと年齢の高い子供であれば、一般的な1人分の金額として2~3万円を追加する場合もあります。
結婚式を欠席する場合
結婚式を欠席する場合のご祝儀については、欠席が決まるタイミングや状況によって変わってきます。
出席予定だった結婚式を欠席する場合
出席予定であった結婚式を何らかの事情で欠席する場合は、もともと渡すつもりだった金額を包むのがマナーとされています。

直前の欠席となると、新郎新婦はすでにお料理や引き出物を手配済。
キャンセルもできない場合が多いようです。
また、一度出席と答えてからの欠席連絡は、新郎新婦をがっかりさせてしまうかもしれません。
そのため、お詫びの気持ちも込めて、渡す予定だった金額を包むのが基本マナー。
ただし、欠席連絡の時点で、挙式まで1ヶ月以上ある場合は、お料理などのキャンセルができることもあるので、「お祝いの気持ち」の1万円のみでよいとの声もありますよ。
早い段階で欠席が決まっていた場合
この場合は、欠席連絡をするタイミングによって変わります。
招待状を送る前の打診の段階で、欠席と伝えた場合は、ご祝儀はなしでも問題ないとの声が一般的。
打診された時は出席と答えたが、招待状で欠席と伝えた場合は、披露宴の食事・引き出物代を除いた1万円を包む人が多いようです。
基本の考え方はこのような感じですが、もっとお祝いの気持ちを伝えたいという人は、結婚祝いのプレゼントも贈ってみてはいかがでしょうか。

結婚式を欠席する場合のご祝儀については、こちらの記事で詳しく解説しています。
招待された結婚式を欠席…ご祝儀の金額や渡し方はどうする?【パターン別に解説】
挙式のみの参加で披露宴は欠席する場合
挙式のみの参加の場合も、食事・引き出物代を引いた1万円程度を目安として考えましょう。
挙式のみの場合のご祝儀についてはこちらの記事を読んでみてくださいね。
なお、欠席する場合は現金書留でご祝儀を送ることがあります。
その場合は、欠席するおわびと結婚式の成功を祈る旨を書いた手紙も同封すると丁寧です。
直接会って渡す場合はそのときに伝えられるといいですね。
会費制の結婚式の場合
会費制のパーティーでは、ご祝儀の代わりに、新郎新婦が決めた会費を払います。

そのため、別途ご祝儀を用意する必要はありません。
なお、会費の相場は次のとおり。
| 立食ビュッフェスタイル | 6000~10000円程度 |
| 着席ビュッフェ orカジュアルなコース | 10000~15000円程度 |
| 着席フルコース | 15000~20000円程度 |
招待状に書いてある金額を当日受付で渡すことが多いようです。
会費制の結婚式についてはこちらも読んでみてくださいね。
「会費制結婚式」とは?メリット・デメリットを徹底調査!会費の相場や費用、引き出物についても解説
ご祝儀をもらったことがある相手の場合
新郎あるいは新婦が、以前自分の結婚式のときにご祝儀を包んでくれた場合。
その場合は、自分のときにもらった金額と同額を用意するのが一般的です。
結婚式を挙げない相手の場合
結婚式を行わないふたりへのご祝儀については、披露宴の食事・引き出物代を引いた1万円程度をお祝いとして贈るのが一般的なよう。

お祝いの気持ちを込めて、1万円分のプレゼントを贈るというのもステキですね。
ここまで、ご祝儀の金額相場について紹介してきました。
自分の場合はどの金額にすればいいか、決まりましたでしょうか?
金額が決まったら、ご祝儀袋についても押さえておきましょう。
ご祝儀袋のマナー
金額に合ったご祝儀袋を選ぼう
金額が決まったら、ご祝儀袋を用意しましょう。

ご祝儀袋は以下のようなものを選びます。
・「のし」がついている
・水引は「結びきり」or「あわじ結び」
・水引の色は「金銀」or「紅白」
・水引の本数は「10本」
・「白地」のご祝儀袋
また、中に入れる金額に合った「格」のご祝儀袋を選ぶことも大切なポイント。
それぞれの金額にふさわしいご祝儀袋は、こちらのような感じです。
| 1万円 | 水引やのしが印刷されたもの |
| 2~3万円 | スタンダードなデザインのもの |
| 5~10万円 | 少し大きめで上質なもの |
| 10万円以上 | 鶴や亀などのおめでたい飾りがついたもの |
ご祝儀袋の選び方については、こちらの記事も読んでみてくださいね。
種類によって意味が違う!?結婚祝いにふさわしいご祝儀袋の選び方!
ご祝儀袋は袱紗(ふくさ)に包もう
お札を入れたご祝儀袋を持ち運ぶときには、「袱紗(ふくさ)」を使いましょう。

ご祝儀袋を汚したり折れ目をつけたりしないようにする意味があります。
袱紗の色はさまざまですが、お祝い事である結婚式では赤やオレンジ、ピンク、金
といった暖色系で明るい色のものが好ましいとされます。
また、紫は慶弔どちらでも使える色とされています。
袱紗についてはこちらの記事でくわしく解説しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

そのほか、ご祝儀についてのマナーはこちらの記事でも紹介しています。
【結婚式ご祝儀】金額やご祝儀袋選びどうする?ご祝儀マナーの基礎知識
結婚式でご祝儀を渡すタイミングや渡し方については、こちらをどうぞ。
ご祝儀にまつわるQ&A
最後は、ご祝儀についてのギモンにQ&A形式で答えていきます!
Q.新札を包んだ方がいいの?
A.ご祝儀として贈るお札は、新札を用意するのが一般的。
新札は、発行されてから使われたことのない「新品のお札」のことで、お祝い事で贈るお金には新札を使うと良いとされています。
似たものに「ピン札」がありますが、こちらは使われたことがあるものの、シワがなく綺麗なお札のことを指します。

新札は、銀行の窓口や両替機、郵便局の窓口などで両替するのがポピュラーです。
新札についてはこちらの記事も読んでみてくださいね。
結婚式のご祝儀は新札で用意するべき?新札はどこで手に入るの?
Q.親から子供にご祝儀は渡す?
A.結婚式の費用をふたりが負担する場合に、結婚式当日のご祝儀としてお金を贈る場合があるようです。
結婚式の費用は、親から資金援助を受ける新郎新婦が多いです。
ただ親からの援助を受けず、新郎新婦で結婚式費用を負担する場合は「お祝い」という形で親からご祝儀を渡すこともあるようです。

この場合、金額は10~30万円ほどを包むことが多いよう。
地域や家庭によって考えは異なるので、金額は両家で話し合ってもいいかもしれませんね。
親からの資金援助についてはこちらの記事でも紹介しています。
親からの結婚祝い・ご祝儀の相場や平均金額は?みんなもらってるの?
※「結婚スタイルマガジントレンド調査2018」
結婚に関するWEBアンケート調査
調査対象:24~69才の男女
調査時期:2018年7月
対象人数:男性500人 女性500人
まとめ
結婚式のご祝儀の相場をご紹介しました。
ご祝儀の基本的な相場は1人あたり3万円。
ただし、新郎新婦との関係によって、相場が少し変わります。
親族の場合は、相場とは別に親族間のルールがあることもあるので、親などに相談するといいですよ。
夫婦や子供と一緒に招待された場合は、人数と用意してもらう料理の代金などを考えて金額をプラスします。
ご祝儀の金額以外にも、ご祝儀袋の選び方や当日の渡し方についても確認しておくと安心ですよ。
「お祝いの気持ち」がしっかり伝わるよう、ご祝儀を渡したいですね!
「結婚式のご祝儀」の他の記事
「結婚式のご祝儀」
の次に知っておきたいこと
- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」
- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」
- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」
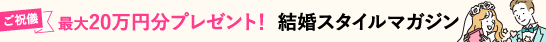
 クリップ記事
クリップ記事