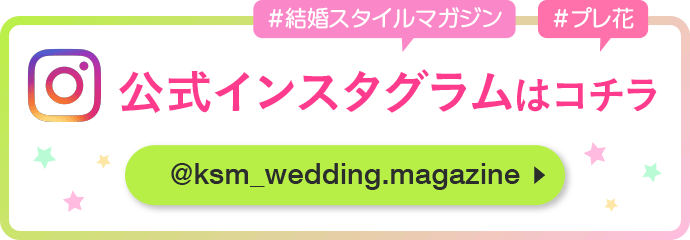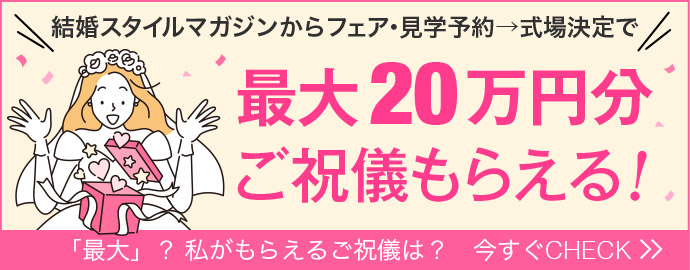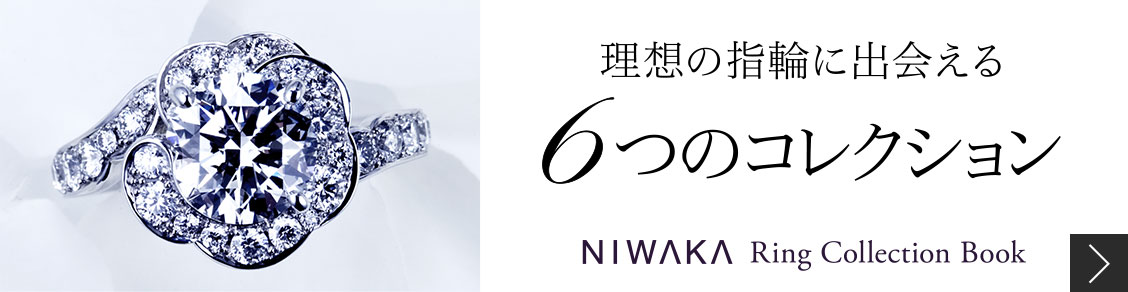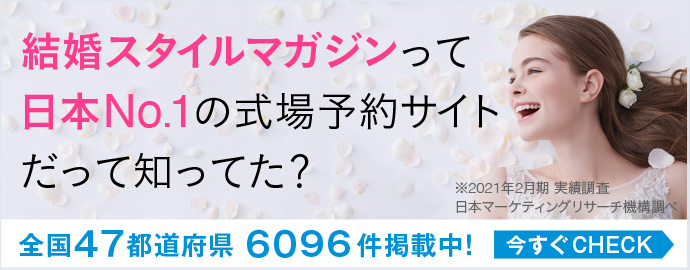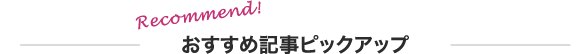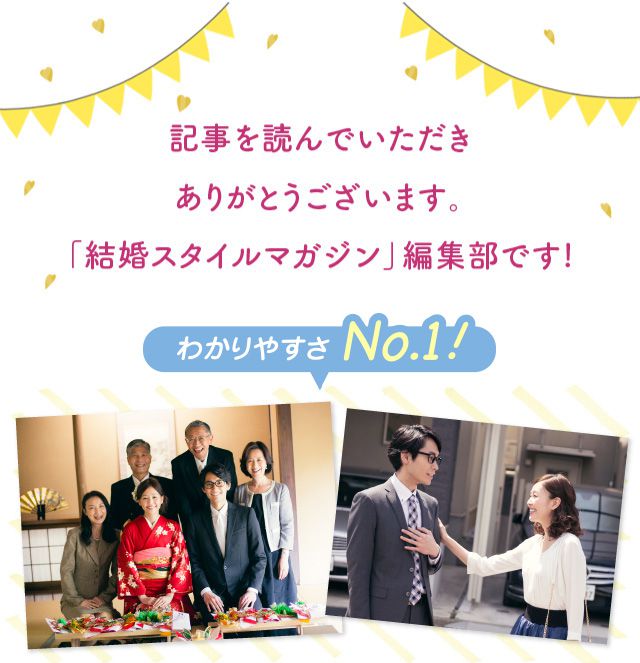挙式のみの結婚式に招待された場合、ご祝儀って必要?相場やマナーは?
音声で聴く!

披露宴をしない「挙式のみ」の結婚式に招待されたときのご祝儀って?
「挙式のみでもご祝儀は贈ったほうがいい?」
「ご祝儀は不要と言われたら?」
そんなギモンにお答えすべく、今回は挙式のみの結婚式のご祝儀に対する考え方を解説します。
立場別の金額相場や渡すタイミングなども解説するので、ぜひ参考にしてください。
挙式のみの結婚式ではご祝儀は必要?
結婚式にお呼ばれした場合、参列者はご祝儀を持参するのが一般的ですが・・・
披露宴のない「挙式のみ」の結婚式に招待された場合、ご祝儀は必要なのでしょうか?

実のところ、挙式のみの結婚式でのご祝儀については明確なルールがありません。
一般的には、「挙式のみでもご祝儀は渡すべき」と考えている人が多いようです。
「ご祝儀はお祝いの気持ちで渡すものだから」
「自分が結婚した時にご祝儀をもらったから」
など、その理由はさまざま。
ではご祝儀を贈る場合、金額はどのくらいにするべきなのでしょうか?
挙式のみの結婚式で包むご祝儀の金額相場を見ていきましょう。
挙式のみの結婚式でのご祝儀相場は?
挙式のみの結婚式では、「挙式+披露宴」の一般的な結婚式に参加するときに包む金額から「食事や引き出物の代金」を引いた金額を包みます。
というのも、挙式のみの結婚式では披露宴の食事がなく、引き出物も用意されていないことが多いためです。
例えば、友人として「挙式+披露宴」の一般的な結婚式に出席する場合のご祝儀は3万円が相場ですが・・・
この3万円は、
○披露宴の食事や引き出物の代金:2万円
○お祝いの気持ち:1万円
といった内訳になっています。
ここから、お祝いの気持ちの1万円だけを包んで渡すんですね。

もちろん「挙式のみでも普段通りの金額を包む」という選択も間違いではありません。
でもあまりに高額のご祝儀を贈ると、
「披露宴もしていないのに申し訳ない・・・」
と新郎新婦を恐縮させてしまうこともあるので、基本的には「お祝いの気持ち分の金額を包む」と考えておくといいでしょう。
普段通りの金額かお祝いの気持ち分の金額かで迷った場合は、ほかの参列者に相談してみてもいいですね。

なお、披露宴の食事や引き出物の代金はどの立場の人でもほとんど変わりませんが、お祝いの気持ちとして包む金額は、贈る立場や新郎新婦との関係性によって変わります。
そこで続いては、挙式のみの相手に贈る場合の金額相場を立場別に見ていきましょう。
挙式のみの相手に贈る立場別のご祝儀相場
先ほど少し触れましたが、挙式のみの相手に友人としてご祝儀を贈る場合の相場は1万円です。
そのほか立場別のご祝儀相場については、
・親族として贈る場合
・職場関係の人として贈る場合
に分けて紹介していきます。
親族として贈る場合
親族といってもさまざまな立場がありますよね。
贈る立場ごとの金額相場は次のとおりです。
・兄弟姉妹として贈る場合:1~7万円
・甥姪、いとことして贈る場合:1~3万円
・おじおばとして贈る場合:3~7万円
いずれも、挙式+披露宴の場合のご祝儀から食事や引き出物代を引いた金額となっています。

ただし親族間では、ご祝儀に関して独自の決まりがある場合も少なくありません。
例えば、
「親族間では、一律3万円を贈りあおう」
「お互いご祝儀はなしにしよう」
といった慣習がある場合も。
まずは親や兄弟姉妹に相談して、ご祝儀の額を決めると安心ですよ。
職場関係の人として贈る場合
・職場の同僚(先輩・後輩・同期)
・部下
といった立場で贈る場合は、友人と同じく1万円を贈るのが相場のようです。

一方、上司として贈る場合は、役職にもよりますが1~3万円が相場になります。
同僚や部下の場合より少し多めの金額になるイメージですね。
ただし、職場でも親族間と同様に、ご祝儀に関する独自の決まりがある場合も。
金額や贈るかどうかについては、あらかじめ職場内で確認しておくといいですよ。

立場別のご祝儀相場については、こちらの記事でもくわしく紹介しています。
【結婚式ご祝儀の相場】いくら包む?会社・友人・親族などの立場やケース別のマナーを解説!
こんな場合どうする?ケース別のご祝儀相場
立場別の相場を紹介しましたが、立場の他に
・夫婦で出席する場合
・過去に自分の結婚式でご祝儀をもらった場合
といったケースの違いによってもご祝儀の相場は変わってきます。
それぞれ見てみましょう。
夫婦で出席する場合
夫婦で出席する場合は、立場ごとの金額の倍額をキリのいい金額に調整して包みます。
特にご祝儀では奇数の金額がよいとされているので、偶数になってしまう場合は少し多めに包んで奇数になるよう調整することがあるようです。
例えば、友人の結婚式に夫婦で出席する場合は1万円の倍の2万円となりますが、偶数を避けて1万円を上乗せし、3万円を包むといった流れです。

また2万円のうち1万円分を商品券やギフトで渡したり、5千円札2枚にしてお札が3枚で奇数になるようにしたりといった工夫も。
今後のお付き合いも考えて金額を決められるといいですね。
ちなみに、夫婦のどちらかが欠席する場合は、相場額から差し引いたりせずにそのまま渡すのが一般的ですよ。

自分が既にご祝儀をもらっている場合
自分が先に結婚していて、新郎新婦からご祝儀をもらったことがあるケース。
「お祝いの気持ちを存分に伝えたい」という場合は同額包むと丁寧です。
ただ、挙式のみの場合の相場通りの金額でも問題ないという意見も多いようです。
親族の場合は挙式+披露宴の場合と同額を贈ることが多いようなので、親族間で相談しておけると安心ですよ。

「ご祝儀はいらない」と言われた場合
新郎新婦から事前に「ご祝儀は不要」という案内があることも。
その場合は、ご祝儀を用意する必要はありません。
新郎新婦の中には、挙式のみの結婚式でご祝儀を頂くのは申し訳ないと感じる人もいるようで・・・
「ご祝儀はご遠慮ください」
というように、招待状でアナウンスされることが多いようです。

でも、
「本当に持っていかなくて大丈夫!?」
「もしほかのゲストが持ってきていたら・・・」
と不安に思う人もいるかもしれません。
ご祝儀を持っていくかどうか迷ったときには、一緒に参列するゲストに相談してみましょう。
親族の結婚式なら親族に、友人の結婚式なら同じ立場の友人に、「ご祝儀はどうする?」と相談しておけば安心です。

プレゼントを贈るという選択肢も
挙式のみの結婚式なら現金ではなくプレゼントを渡すというのもアリ!
現金で渡す場合の金額相場を基準に、新郎新婦が喜びそうなものをチョイスすると喜んでもらえそうですね。

プレゼントの一例は、こちら。
○新生活に役立つもの
キッチン用品、ブランド食器、高級タオルなど
○新郎新婦の好きなもの
お酒、食べ物、趣味で使うものなど
○新郎新婦が選べるもの
カタログギフトや商品券など
新郎新婦と親しい間柄なら、欲しいものを聞いてプレゼントするのもいいですね。
また、友人数名で連名として高価なプレゼントを贈るのもステキですよ。

また、新郎新婦に現金でのご祝儀は辞退されているものの「それでもお祝いしたい!」という場合にも、プレゼントを贈るのはおすすめ。
数千円程度のプレゼントなら、そこまで気をつかわせてしまうこともなさそうですよね。
では最後に、ご祝儀やプレゼントを渡すタイミングについても見ていきましょう。
ご祝儀はどのタイミングで渡す?
挙式のみの場合、ご祝儀やプレゼントを贈るなら結婚式より前に渡すのがベスト。
特に重いものや大きなプレゼントは、事前に自宅へ郵送しておいたほうが親切です。

ご祝儀だけを郵送する場合や、ご祝儀とプレゼントを一緒に郵送する場合は、郵便局から「現金書留」で送りましょう。
詳しい送り方については、こちらの記事を読んでみてくださいね。
ご祝儀は郵送してもOK?現金書留での送り方やメッセージ、一緒に贈るプレゼントなどについて紹介
もし結婚式当日に渡す場合は、タイミングに注意が必要です。
挙式のみの結婚式は基本的に次のような流れで行われます。
1 受付
まずはゲスト全員が受付を済ませます。2 挙式
挙式が執り行われます。
だいたい20~30分程度が一般的です。3 アフターセレモニー
挙式会場の外に出て、フラワーシャワー、ブーケトスなどゲストも参加して色々な演出が行われます。4 集合写真撮影
新郎新婦とゲストで集合写真の撮影です。5 フリータイム
新郎新婦とゲストが歓談できる時間です。
受付がある場合は、一般的な結婚式と同じようにご祝儀は「受付」で渡すのがベスト。

でも挙式のみの結婚式では、受付が設置されていないことも。
その場合は、最後の「フリータイム」がおすすめのタイミングとなります。
挙式中はもちろん、アフターセレモニー中や集合写真を撮ろうとしているときに渡すのはNG。
新郎新婦が考えた演出・進行が優先なので、流れを止めてしまうようなことは避けたいですね。
フリータイムなら自由に動けるので、ご祝儀も渡しやすいですよ。

ただし、ご祝儀を結婚式中に渡す場合、新郎新婦本人に渡すのはあまり好ましくありません。
ゲストと交流し、結婚式を楽しんでいる二人に現金を差し出すというのは、なごやかな雰囲気を少し濁してしまうことにもなりかねないからです。
ご祝儀を渡す場合は、新郎新婦の親や担当スタッフに渡すようにしましょう。

ちなみにプレゼントの場合は、適度な大きさならフリータイムやお見送りの時に手渡しするという方法もアリ。
事前にスタッフに相談してタイミングをとってもらえる場合は、サプライズ演出として渡すのもいいですね。
まとめ
挙式のみの結婚式に参列する場合の、ご祝儀についてご紹介しました。
挙式のみの結婚式ではご祝儀は必須ではありませんが、一般的には「ご祝儀が必要」と考える人が多いよう。
ただし、新郎新婦からご祝儀を辞退する旨の案内があったときは不要となります。
ご祝儀の金額相場は、挙式+披露宴の結婚式で「お祝いの気持ち」として包む分の金額を包めばOK。
友人の場合は、一般的なご祝儀3万円から料理や引き出物代の2万円を引いた1万円となります。
立場によっては金額相場が変わってくるので、注意してくださいね。
このほか、現金ではなくプレゼントを贈るのもアリ。
前もって渡すことができれば理想ですが、結婚式当日に渡すなら、受付かフリータイムの時がベストです。
また、新郎新婦本人ではなくご両親や担当スタッフに預け、後で渡してもらうようにしましょう。
お祝いの気持ちをきちんと伝え、新郎新婦を祝福したいですね!
結婚式ご祝儀の一般的なマナーについては、こちらの記事も読んでみてくださいね。
【結婚式ご祝儀の完全マニュアル】金額相場やご祝儀袋の選び方・書き方・渡し方などを一挙紹介
「結婚式」の他の記事
「結婚式のご祝儀」
の次に知っておきたいこと
- 結婚に関する疑問を解決したい方へお役立ち記事2100本!「結婚ラジオ」
- 結婚のあれこれ、スキマ時間に楽しく読みたい方へイメージ膨らむ♪「結婚準備の基礎知識」
- 結婚式場を決めたい、お得に結婚式を挙げたい方へ全国約2000式場をご紹介「結婚式場を探す」
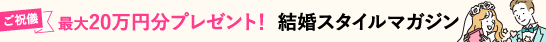
 クリップ記事
クリップ記事